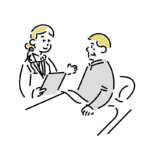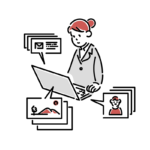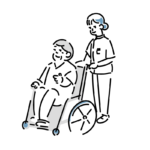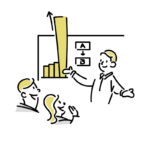政策アイデア・マニフェスト
これからの奄美市についての基本理念
私は、奄美には、よそにはないここだけの宝がたくさんあると信じています。独特の自然環境、歴史、伝統文化、地場産業、その他無数にありますが、最高の宝は「人のやさしさ、温かさ」であると感じています。
私にとっての奄美の原点は、祖父母から注がれた惜しみない愛情ややさしさです。奄美に暮らす多くの方々が、誰かの温もりであったり、さきに述べたいくつもの宝であったり、都会にはない、奄美にこそ根強くある無数の価値を信じ、愛し、大切にしていると考えております。
その一方で、地域には多くの課題や問題が横たわっています。全国の地方や離島にも共通する点はありますが、人口減少や少子高齢化の加速度的進展、地域の経済や産業の著しい衰退、低所得や格差拡大・貧困の問題、労働力や地域団体の担い手の不足などです。また、医療・介護・福祉・教育・防災・環境・自治体財政などの面でもそれぞれに多くの課題や問題を抱えています。
そして、新型コロナウイルス感染症により、私たちの生活様式・行動様式など、社会や経済、そして地域のあり方も大きく変わってきています。「海外と比べて10年以上遅れている」と指摘されるわが国のデジタル化への取り組みにおいて、行政・仕事・医療・教育などで新たな技術の活用が生まれつつあります。地域として一つの大きな目標である世界自然遺産登録が実現された今、国際化(グローバル化)もさらに進んでいきます。この南西諸島全体が大きく変わろうとしています。
この奄美市を取り巻く状況は、いわば「課題や問題の集積地」であり、本土と比べて様々な課題が顕在化・多様化・進行しています。奄美が「日本の縮図」といわれ、そしてこれからもそうあり続けるであろうと考えます。
これは裏を返せば、地方や離島の課題解決のモデル地域になり得るということです。いや、私は、この奄美市を全国から注目される課題解決のモデル都市にしたいのです。課題先進地だからこそ、これまでの取り組みで継続すべきことを見極めつつ、社会や時代の動きに応じて新しい感性や大胆な発想・アイディアを積極的に取り入れ、優れた人材・知恵・情報・技術を集約・活用して、課題解決に向けスピード感をもって地域に関わるみんなで努力・実践していくことが最も重要であると考えます。
私は、42歳の若さとパワー、市議3期の経験を最大限発揮し、これからも「市民の皆様の思いに寄り添い、市民の皆様と何度でも対話し、市民の皆様とともに汗をかく」姿勢を貫き、新しい時代に対応する未来都市・奄美市を目指します。

奄美市のビジョンとマニフェスト(選挙公約)の考え方
「明るく やさしく 風通しのよい 未来都市・奄美市」
奄美市の将来ビジョンとして、私はこのような姿を思い描いています。
「明るい」とは、奄美市に住む・奄美市を訪れる皆様の表情が明るいということ。また、まちに活気があり、雰囲気が明るいということ。ワクワク感があり、楽しいまちであることです。
「やさしい」とは、奄美市の皆様が、子どもでも障がい者でも、若者でも高齢者でも、また、性別などにも関係なく、分け隔てなくお互いを思いやり、助け合い、誰一人置き去りにしないで、安心して暮らせること。また、環境にもやさしい行動をとり、負荷をかけすぎず、山や海、生き物など世界に誇れる貴重な自然環境を守り、持続可能なまちであることです。
「風通しのよい」とは、出身・世代・性別・経歴・職業などにとらわれず、お互いを尊重し、皆様が意見を言い合える、活発に話し合いができること。狭い世界観での足の引っ張り合いやコップの中の争いをやめ、公正・公平に競争したり協力したりしながら、お互いに成長や繁栄することを目指して磨き高め合うまちであることです。
「未来都市」とは、Society5.0やSDGs(持続可能な発展目標)など政府や国際機関が提唱する新しい理念を積極的に取り入れ、新しい知恵・情報・技術を最大限に活用して、既存の知恵や手法と融合させながら、地域社会の諸課題をより良く解決できるよう取り組む姿が定着していること。子どもや若者たちがふるさと奄美に愛着を持って将来帰って来たくなり、若い世代のチャレンジをみんなで応援し、次世代を受け継ぐ人材が着実に育っていくまちであることを意味します。
このビジョンの実現に向けて努力する過程において、奄美市が掲げる「しあわせの島」を本気で目指すために、より具体的に、以下のような姿が達成されることを目指します。
1.民間(企業・団体等)にとって、市役所との協力・連携体制がより良く、より強く進み、それぞれに持てる力を十分に発揮して、地域の「かせぐ力(経済的な豊かさを生み出す力)」が向上している。多くの市民の所得が増え、経済的にも精神的・身体的にもゆたかさを感じて、幸せを実感している。
2.市民にとって、市役所がより身近な存在となり、頼れる相談相手となっている。全ての市役所職員が市民の皆様に対する奉仕者であるとの認識を持ち、親切丁寧をモットーとして、ICT(情報通信技術)の活用により、市民の皆様の声が市役所に届きやすくなり、市民サービスの品質やスピードや満足度が向上し、幸せを実感している。
3.市役所職員にとって、公正・公平な人事が行われ、生きがいや働きがい、そして誇りを感じる職場となっている。常に仕事環境の改善を志向し、ICT等の活用により縦割りの旧弊を打破し、スピーディーな情報の共有化を図ることであらゆる関係者との円滑なコミュニケーションが根付き、市民サービス最優先の仕事ができて、幸せを実感している。
4.議会議員にとって、市役所の情報公開がさらに進み、議会活動へのモチベーションが向上している。二元代表制としての役割を最大限に果たしていくために、一定の緊張関係を保ちつつ、お互いに切磋琢磨しながらも同じベクトルに向かって協力する関係が構築できて、幸せを実感している。
このビジョンの実現に向けて、これまでの必要な政策や事業の継続を前提としつつ、新しい時代に対応するための取り組みとして、次のような政策・事業を提案し、実行してまいります。マニフェスト(選挙公約)の作成に当たっては、
Ⅰ 新型コロナウイルス対策
Ⅱ 持続可能に「かせぐ」地域づくり
Ⅲ 安心して、ゆたかにくらせる「まもる」地域づくり
Ⅳ 次世代を育む好循環を生み出す「そだてる」地域づくり
Ⅴ 市民に身近で頼りになる基盤づくり
という5つのテーマに沿って集約しています。皆様のご意見ご指導をお願いいたします。
マニフェスト(選挙公約)
Ⅰ.新型コロナウィルス対策
徹底した感染防止対策と経済対策を両立し、「感染症に強い島内体制」を構築します。
【1】新型コロナから市民のいのちを守ります。
地域医療機関をはじめ関係機関との情報共有・連携体制を常に維持・強化し、PCR検査拡充やワクチン接種の推奨、医療体制の充実や軽症者向け宿泊療養施設の増設、自宅待機者(自宅療養者)も安心して医療を受けられるしくみの構築に取り組みます。あわせて、家庭・職場・会食などでの感染防止対策等、新型コロナや今後も出現する新たな感染症対策の情報発信を徹底し、「感染症に強い島内体制」を構築します。
【2】新型コロナから地域を守るため、水際対策を強化します。
新型コロナ警戒レベルに応じてPCR検査やワクチン接種が未済の来島者に向けて、空港・港での抗原検査実施やマスク配布などを行い、感染防止に向けた注意喚起を強化します。あわせて、ホテルやレンタカー事業者との連携を強化し、旅行者に向けた注意喚起を徹底します。
【3】新型コロナから地域経済を守ります。
新型コロナで特に大きな影響を受けている飲食・観光・レジャー及びそれらに関連する業種に対して、「新型コロナ対策官民連携協議会」の議論や各経済団体等からの要望を踏まえて、事業者への直接支援や需要喚起策、また生活者支援などをスピーディーに行います。
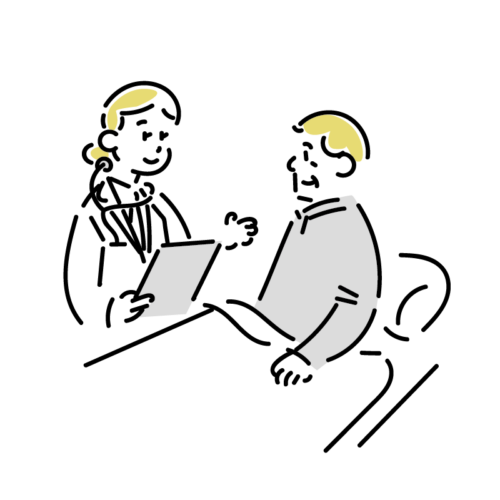
Ⅱ.持続可能に「かせぐ」地域づくり
ゆたかで幸せな奄美市をつくるために、また、教育や福祉の充実のためにも、「観光×物産×情報通信」を柱として、経済や産業の成長・発展に全力で取り組み、地域内総生産額を高め、人口一人当り所得の向上を目指します。
〇観光客一人当り消費額の増加を目指す取り組みの強化
【4】観光・交流の高度化・高付加価値化を推進します。
観光は奄美のリーディング産業、外貨獲得の大きな柱です。コロナ後の誘客増加は確実なものであり、観光客一人当たりの島内消費額増加を目指して、奄美大島DMO(観光地域づくり法人)の「奄美大島中期観光戦略」に磨きを掛けます。また、宿泊・飲食・交通など受入環境の整備・おもてなし力の向上に向けて事業者との連携を強化するとともに、施設・接客・サービス・地場産品を柱とした商品の磨き上げ支援を行い、高付加価値化、つまり、今よりもかせぐ力の強化を目指します。
【5】世界自然遺産の価値を守る公民連携の組織をつくります。
世界自然遺産の本来の目的は、世界的にも希少な、この地域特有の自然環境と生物多様性を保全すること。国立公園においては、さらに環境文化を保全することも重視されています。観光への活用を期待しつつも、その価値を持続可能に保全し高めていき、かつ経済効果を最大化するために何が必要かを議論し戦略を立案する公民連携のシンクタンクを創設し、政策の実現性を重視しつつ具体的に活動していきます。
【6】観光や特産品の情報発信・広報を強化します。
発信力や企画力・デザイン力をもつ若い世代を中心に、インターネットを通じた観光や特産品の情報発信を後押しし、奄美のブランド力向上につなげる取り組みを展開します。また、メンタルヘルスやリトリートに資する「癒し」など、新たな価値の提供により誘客につなげます。
【7】新しい価値観に基づく観光・交流の多様化を推進します。
市民の皆様のご理解とご協力を頂きながら、集落歩き・集落行事への参加や自然の中での様々な体験など、アドベンチャーツーリズム(高付加価値な体験型観光)普及のための人材育成・体験メニューの開発支援に取り組みます。また、ワーケーションやキャンプ・グランピング・短期移住など、多様なニーズに応えられる施設・環境整備を民間と連携しながら進めます。
【8】観光・交流の経済波及効果拡大を実現します。
交流人口増加による地域経済への波及効果の伸びは、奄美経済全体の発展に必要です。ICT(情報通信技術)の活用により農林水産業・飲食業や大島紬・黒糖焼酎などの他業種との連携強化(体験メニュー参加や購入・消費)に取り組むとともに、リピーター獲得を重視して、付加価値の高い加工品・特産品の定期継続的な購入に結び付ける取り組みを展開します。
【9】ユニバーサル・ツーリズムの展開を進めます。
高齢の方や身体の不自由な方、障がいの有無にかかわらず、誰もが気兼ねなく楽しめるユニバーサル・ツーリズムの普及を促進し、美しい奄美の島旅を提案していきます。そのために、公共施設や観光施設のバリアフリー化や多目的トイレの増設、役に立つ情報発信を進めます。
【10】南西諸島での人の流れや物流を活発化します。
世界自然遺産を基軸として、奄美群島内や屋久島・沖縄との地域間連携強化を進め、南西諸島における観光や物産、人材の交流を進めます。
【11】国内・海外からの誘客を促進します。
新型コロナの収束を見すえて、国内・海外のターゲット(欧米・アジアの富裕層など)を調査・分析して、ニーズを満たすプレミアム感のある奄美の情報を発信し、スムーズな誘客につながるよう他市町村や観光関連団体等と力を合わせながら、新しい航空ルートや人数を限定したハイクラスを含めたクルーズ船の誘致に取り組みます。
〇「かせぐ地域」をつくる経済政策
【12】全ての中小企業・個人事業者支援を推進します。
地域経済の重要な基盤であり、雇用の受け皿でもある中小企業や個人事業者が思う存分に活動・活躍できるよう、民間の経済団体や金融機関等と連携して、人材の確保・育成、補助金・助成金などの情報提供・相談、資金供給の円滑化など、徹底した支援策を行います。また、フリーランスをはじめとした起業家に対する経営ノウハウの提供やコンサルティング、業種転換や新分野への進出支援も積極的に行います。
【13】「食と農の総合戦略」をつくり、実行します。
奄美の宝でもある食文化を守り発展させるために、ガストロノミー(食事学)などの考え方を参考に、「食と農の総合戦略」をつくり、農林水産業の振興や食育による健康長寿の促進、食文化の承継や観光との連携に取り組みます。あわせて、島野菜の増産、島豚や地元産水産資源の有効活用、ジビエ料理の展開、担い手の確保など、中長期的視点での取り組みにもつなげます。
【14】農業支援を継続・強化しつつ、スマート農業を推進します。
さとうきび・畜産・野菜・果樹等の生産力向上に向けた取り組みを強化しつつ、最先端のロボット技術やICTを活用したスマート農業(省力化・精密化や高品質生産を実現する新しい農業)の展開により、安心安全かつ効率的な「かせげる農業」の実現を推進します。
【15】新規・若手就農者への支援を強化します。
新規・若手就農者の経営がより円滑に成り立つよう、国の農業次世代人材投資資金や市の研修制度等に加え、マーケティングや販売力強化のための支援を行い、仕事の魅力度アップに取り組みます。また、休耕地のさらなる活用による支援も強化します。
【16】付加価値の高い農林水産物や加工品の生産支援を行います。
薬草・コーヒーの栽培促進や商品化、陸上養殖の導入に向けた調査・研究、保存が効くレトルトパウチ・冷凍食品製造のための食品加工施設の整備・最新機器の導入、黒糖菓子類の磨き上げによる新しいスイーツなど特産品づくりの支援、マーケティングや販売促進支援など、食と農のかせげる商品づくりを支援します。
【17】「かせげる漁業」づくりに取り組みます。
漁業従事者の維持・確保は地域の大きな課題です。若い担い手が就業したいと思えるような生産・流通・飲食店・行政が一体となった「お魚一店舗一品運動」の展開による地元魚食の普及など、漁業の振興に取り組みます。
【18】ものづくりと販売の支援を推進します。
大島紬などの工芸品や新たな価値を生むハンドメイドなどについて、マーケティングによる多用途化やデザイナーとのマッチングなど、新しい知恵や発想によるものづくり支援を行います。また、黒糖焼酎など食と農の加工品を含めて、電子商取引(EC)での国内外への販路開拓を業界・事業者ごとに支援し、外貨のさらなる獲得を目指します。
【19】情報通信産業の企業・仕事・人材誘致を推進します。
新しい時代の経済社会を目指すためにも、ICT人材の誘致・確保・育成は地域にとって大事なテーマであり、内需・外需を含めた経済力を生み出す産業の柱となります。これまでに整備した情報通信産業拠点の活用や中心商店街との連携により、関連する企業・仕事・人材を誘致するとともに、「場所を問わない働き方」に資するための通信環境整備と広報に取り組みます。
【20】地元産業と情報通信産業の提携を強化します。
「ICT見本市」を開催して、スマート農業の展開、観光情報の発信、観光体験メニューのネット予約システム、オンラインツアー、キャッシュレス決済の推進、観光と他産業との連携情報の発信、物産のマーケティングや電子商取引での販路拡大など、地元産業と情報通信産業の連携強化を支援し、地元産業の収益向上を目指すとともに、地元情報通信産業の仕事・事業の創出にも結び付けます。
【21】民間との連携強化により、投資や実証実験を呼び込みます。
民間企業・団体などが活動しやすい制度・環境整備やオープンデータの推進を行うことにより、PPP(公民連携による公共サービスの提供)・ PFI(民間資本による公共施設整備)や企業・事業誘致が進むように取り組みます。また、新しい技術であるドローン・AI・クリーンエネルギーや産業・医療・介護・教育・公共交通におけるICT活用などの実証実験に民間と連携して取り組み、離島における地域モデル創出を目指します。
【22】主要インフラの整備を進めます。
生活道路・産業道路であり、また観光や防災にも資することから、大熊-有良間、住用町城、三儀山などのバイパス整備促進のために基礎調査を進め、進捗を報告します。また、公共工事について施工時期の平準化を促進します。さらに、港湾や海岸への軽石漂着問題など都度発生するインフラ課題についても、国や県と密接に連携して必要な処置を行うべく迅速に調査・分析・対応します。

Ⅲ.安心して、ゆたかにくらせる「まもる」地域づくり
市民がゆたかで幸せにすごすために、くらしの安心感や満足感、健康づくりは重要です。奄美の大事な価値である「ウェルネス(健康・癒し・長寿)」を高めるべく、医療・福祉の充実や環境・ 防災にも力を尽くして、ひとに自然にやさしい地域を目指します。
〇「ウェルネス」を高める医療・地域福祉の充実
【23】医療との連携を強化し、市民の健康づくりを進めます。
医療機関や薬局との連携を進め、疾病予防や介護予防、早期発見・早期治療を主眼とした特定健診やがん検診の受診率向上に向けた取り組みなど、市民の健康づくりを推進します。また、糖尿病・高血圧症・認知症・脳疾患などのリスクの見える化をヘルスケアICT企業の協力をもとに実施し、その予防・改善のための食事・運動・休養等の取り組みにつなげます。
【24】「断らない命と福祉の相談窓口」を設置します。
厚生労働省が推奨する「重層的支援体制整備事業」などを活用し、高齢者の孤立・孤独死、中高年のひきこもり、自殺防止など、制度の狭間の問題にも対応できる「断らない命と福祉の相談窓口」を民間とも連携しながら開設し、困っている方々・悩んでいる方々、弱い立場にある方々を徹底して支援します。
【25】健康に年を重ねられる地域づくりを進めます。
主に高齢者を対象とした「地域健康教室」や「ころばん体操教室」などを参考に、「地域サロン」を市内各地に設け、地域の中でのつながりを大事にしながら心身ともに健康にすごせる環境づくりを進めます。また、介護度の重度化を防ぐとともに、改善または維持が図れるような取り組みを推進します。さらに、行政による老人クラブへの支援強化を目指します。
【26】元気な高齢者の就労づくりを支援します。
元気な高齢者が後継者のいない農家を支援したり、民間事業所の定型作業や軽作業を担ったり、地域の語り部ガイドとして活躍したりして、シニア世代も年金プラスアルファの収入が得られるしくみをつくります。
【27】高齢者の尊厳をまもる取り組みを強化します。
成年後見制度の利用促進、高齢者虐待防止、地域みまもり制度、認知症の高齢者や家族をサポートするしくみづくりなど、高齢者の尊厳をまもる取り組みを進めます。
【28】介護人材などの確保・育成に取り組みます。
高齢者福祉などで働く介護人材の確保・育成は、全国的な課題です。本市においても、高校・専門学校との連携や外国人材の活用も視野に、地域を挙げて介護人材を確保・育成することに取り組みます。また、介護分野における新しい技術の活用も進めます。
【29】重度心身障害者等医療費制度の手続き簡素化を進めます。
県と連携し、重度心身障害者等医療費制度の手続きを、自動償還払い方式の導入など簡素化できるよう取り組みます。
【30】障がい者の収入が増す取り組みを目指します。
障がい者就労施設への仕事の発注や物品調達を意識的に増やし、働きがいや収入が増すしくみをつくります。また、「農福連携」において、農業の観点からの支援強化を進めます。
【31】誰もが住みやすい地域づくりに取り組みます。
公共施設や公園などのバリアフリー化・ユニバーサルデザインの導入に積極的に取り組みます。また、情報保障としての手話・要約筆記派遣事業の充実など、障がいや様々な困難を抱える方々のニーズに応えられる施策の充実を図ります。
【32】公共施設における分煙環境を整備します。
アイアイひろばなど公共施設への分煙環境を整備し、たばこを吸う人も吸わない人も快適に過ごせる環境づくりを目指します。
〇市民の暮らしと安全をまもる地域防災・防犯の強化
【33】災害に応じた避難所等の増設・充実に取り組みます。
近年、激甚化してきている台風や大雨、数十年のうちに発生が想定されている大地震や大津波などに備えて、それぞれの地域に合った新型コロナ対応型避難所や一時避難場所の整備を進めます。地震・津波など急を要する災害への周知を徹底することで、「逃げ遅れゼロ」の島を目指します。
【34】災害情報の伝達を強化します。
地元コミュニティFMとの連携をさらに強化して、防災ラジオなど新機器を導入・普及することで、災害情報が適時に途切れなく全ての市民に行き届き、適切な避難行動につながるよう伝達力の強化を進めます。
【35】民間企業・団体の防災に向けた取り組みを支援します。
災害発生時に協力を頂ける企業・団体と平常時から連携体制を強化して、避難訓練や非常食・飲料水等必要物資の備蓄など、地域の安全と事業の継続をまもるしくみづくりを支援します。また、企業との連携により、小中学校における防災教育の強化を目指します。
【36】ペット同伴可能な避難所の整備を進めます。
ペットも大切な家族という考えのもと、地元の獣医師やボランティアの方々と連携し、笠利・住用・名瀬それぞれにペット同室避難可能な避難所の整備を進めます。
【37】防災・減災を進める治山治水事業を進めます。
大雨などの自然災害に備えた法面整備工事や河川拡幅・掘削、堤防強化工事を進めます。その際には、当該地域にお住いの皆様のご意見や、自然環境・生態系に配慮したり再生を促したりするグリーンインフラの視点を加味した工法の導入を検討します。
【38】防犯カメラやドライブレコーダーの設置を進めます。
国内・海外からの交流人口の増加に伴い、犯罪や交通事故が増加するリスクへの備えも考えなければなりません。それらの抑止効果や発生時の早期解決につなげるために、地域における防犯カメラの設置支援や公用車等へのドライブレコーダー設置を進めます。また、地域における街灯・防犯灯の設置を進めます
〇世界自然遺産の価値をまもる環境保全の強化
【39】「奄美大島生物多様性地域戦略」を活用・推進します。
本島5市町村で策定した「奄美大島生物多様性地域戦略」に基づく自然環境の徹底した保全と、自然体験や動植物観察におけるルールづくり、人材育成など適切な活用・推進を図ります。また、希少動植物の盗掘・盗採や外来種対応(植物・ノヤギなど)、ロードキル防止対策についても取り組みを強化します。
【40】生活環境の美化をまもるためのしくみをつくります。
ごみのポイ捨てや不法投棄防止、漂着ゴミの海岸清掃など生活環境の保全について、粘り強い普及啓発をしながら、学校での教育活動や市民・観光客を巻き込んだ実践的な取り組みを展開できる、善意や行動力を引き出すしくみをつくります。
【41】環境保全に特化した、地域独自の財源をつくります。
本島5市町村やあまみ大島観光物産連盟など民間団体との連携を強化して、たとえば宿泊税やチップトイレの導入など、各地域において独自の環境保全活動を支援する財源づくりを目指します。

Ⅳ.次世代を育む好循環を生み出す「そだてる」地域づくり
地域の宝である子どもたちの健やかな成長を願って、子育て支援や教育に民間との連携を強化して取り組みます。また、移住・定住支援や地域・集落・商店街の担い手支援など、次世代が着実に育つ好循環を生み出すしくみをつくります。
〇「地域の宝」を育む子育て支援の充実
【42】子育て世代への支援を強化します。
市役所内にある「子育て世代包括支援センター」を中心に、不妊治療支援や出産支援、産後ケア支援など、妊娠・出産・子育ての相談をしやすい窓口の充実を図り、情報発信を強化して、子育て世代の不安に寄り添う体制整備に取り組みます。あわせて、乳幼児と出かけやすい環境の整備や、子育てが終わった世代の皆様のご協力を得て、子育て世代へのサポートを担っていただくしくみづくりを強化します。
【43】待機児童ゼロの維持に取り組みます。
保育所における待機児童ゼロを目指して、民間との連携も強化しながら、保育・託児施設の拡充に取り組みます。また、保育士確保を強化するために、いわゆる「潜在保育士」の掘り起こしや活用、待遇改善に向けた取り組みを行います。
【44】子育て世代の復職・就業支援に取り組みます。
子育て世代、特に母親が社会との接点をもったり収入を増やしたりするために、仕事をすることは大事なことであると認識しています。時短勤務や在宅勤務を含めて、事業者とのマッチングや企業への雇用奨励など復職・就業支援に取り組みます。
【45】子育て世代への経済的支援に取り組みます。
0-2歳児の保育料無償化や教育バウチャー(クーポン)制度など、子育て世代の経済的負担を軽減するための取り組みについて調査・研究を進め、具体策の立案・実行を目指します。
【46】子どもの貧困対策を強化します。
全国的には「6人に1人が該当する」といわれる子どもの貧困対策について、市内での実態把握に努めるとともに、民間の子ども食堂との連携を強化して、学習支援拠点を併設するなど、子どもの居場所づくり・学び舎づくりを進めます。また、兵庫県明石市を参考に、ひとり親家庭への支援などを盛り込んだ「こども総合支援条例」の制定に向けた調査・研究を進めます。
【47】療育・発達支援を強化します。
幼児期からの療育・発達支援を強化するために、民間機関との連携を強化し、相談窓口の充実や福祉サービスの充実を目指します。また、小中学校の特別支援教育の充実を図るために、専門職の配置拡充に取り組みます。
【48】学童保育不足の改善に取り組みます。
学童保育(放課後児童クラブ)が不足している地域における受け皿の定員増や教育内容の充実、施設整備に向けて、民間との連携により改善・向上を目指します。
〇「次世代の地域の担い手」を育む教育の強化
【49】ICTの活用による学力向上に取り組みます。
文部科学省の「GIGAスクール構想」により小中学生に一人一台配布されたタブレット端末を活用し、習熟度に応じたきめ細かな学習支援を行い、学力向上を目指します。そのために、家庭での持ち帰り学習実施、教育ソフトの充実、教師の研修やICT支援員の充実に取り組みます。また、公共施設など中高生の学習拠点づくりを推進します。
【50】インターネット教育の推進
若年層へのSNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)等の普及により、ネットリテラシー(インターネットを適切に使いこなせる技術・能力)が不十分なまま様々なトラブルに見舞われる危険性が高まっています。小中学校での教育現場において、適正なネットリテラシーや健康保持についての教育を進めます。また、これからの時代には必須項目となるプログラミング教育や国語・英語教育に力を入れていきます。
【51】郷土教育・ふるさと学習の充実に取り組みます。
市内各小中学校における郷土教育について、地域における特色ある取り組みが展開されています。郷土愛やアイデンティティを育むために、奄美の特性である自然・歴史・文化体験を幼少期からの教育に活用します。小中学校においては、自らが暮らす地域に加え、奄美市全体の自然・歴史・文化・地場産業・方言などが学べるよう、市街地の学校と集落を結び、教材・講師・学習方法を工夫して、郷土教育の充実を図ります。
【52】社会経済教育・職業(キャリア)教育の充実に取り組みます。
高校の進路選択や人生の目的・目標設定に活かすべく、小学校高学年からの社会経済教育・職業教育を実施し、できるだけ早い段階で生き方や人生設計、目指す職業、必要な技術・資格・免許などを考える機会の提供に取り組みます。
【53】不登校支援の充実に取り組みます。
「普通教育機会確保法」の趣旨に則り、休むことの必要性や「学校以外の学びの場」の重要性を普及する研修の機会を設けます。また、学校・スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーとの連携強化や適応指導教室(ふれあい教室)の活用を図るとともに、民間のフリースクールなど子どもの居場所づくりや運営支援にも取り組みます。
【54】学校におけるいじめ問題の改善に取り組みます。
子どもや保護者がいつでも気軽にオンラインを含めた多様な手段で、いじめや暴力などについて相談ができる環境を整えるとともに、迅速かつ積極的に学校でのいじめを認知し、関係行政機関を含めた組織的な対応によって重大な事態になる前にいじめを解決に導く体制を構築します。
【55】本土遠征への支援の充実に取り組みます。
離島という大きなハンディの解消を目指して、スポーツや文化・芸術活動における小中学生の本土での大会参加に対する補助を拡充します。また、そのための基金の創設についても調査・研究を進めます。
【56】高校の魅力向上を支援します。
高等学校の生徒確保・学校存続に向けて、奄美の特性の活用など、さらなる魅力向上の支援に取り組みます。また、離島留学制度の導入を調査・研究し、学生寮の整備や教育・人材育成拠点としての活用と活性化を図ります。
〇大人の学び直しや文化・芸術・スポーツ活動への支援強化
【57】学び直しや生涯学習の充実に取り組みます。
学び直し・リカレント教育に、サテライト拠点をもつ大学や大学院など教育機関と連携して取り組みます。また、島口・島唄・文化活動など公民館講座のオンライン開設に向けて、調査・研究を進めます。
【58】文化・芸術活動の活性化に向けて支援を強化します。
文学・音楽・絵画・書道や現代アートなど、あらゆる文化・芸術活動の活性化に向けて、関係団体との連携を強化して、運営支援や活動環境の整備などに取り組みます。
【59】鹿児島国体相撲競技開催への機運づくりを強化します。
令和5年の「鹿児島国体相撲競技」奄美市開催に向けて、事前に盛大なイベントを行うなど、未就学児から大人まで、市民を巻き込んだ機運づくりに取り組みます。
【60】「チャレンジスポーツ」の島づくりに取り組みます。
トレイルラン・自転車・カヌー・ヨット・サーフィン・ウインドサーフィン・SUP(スタンドアップ・パドル・サーフィン)・ビーチバレーなど、奄美の自然環境を活かした競技の誘致や大会開催に取り組み、交流人口の増加や市民参加による地域活性化につなげます。
【61】スポーツ環境の整備に向けて取り組みます。
既存施設の人工芝化によるサッカー・ラグビー場整備など、あらゆるスポーツの競技環境向上を目指します。
【62】eスポーツの振興に向けて取り組みます。
離島でも雨の日でも楽しめるeスポーツ(電子機器を用いて行う娯楽・競技・スポーツ全般)の振興のため、企業と連携してイベントを開催し、eスポーツ選手との交流を企画します。これにより、さらに奄美市をPRします。
【63】奄美群島日本復帰運動の伝承強化に取り組みます。
令和5年の奄美群島日本復帰70周年に向けて、小中学校での郷土の歴史教育への取り入れをはじめ、全市民を巻き込んだ伝承の強化に取り組みます。
〇人口減少に歯止めをかける移住・定住支援の強化
【64】移住希望者に寄り添う相談窓口を設置します。
奄美市への移住・定住相談窓口を強化し、移住希望者に寄り添ったきめ細かな支援を行います。移住経験者を交えた相談会や就職・住居に関する情報提供、移住に向けた生活支援・経済支援などに取り組みます。
【65】地域の空き家を活用した移住促進策に取り組みます。
地域・集落の空き家情報を詳細かつ丁寧に集め、賃貸可能な空き家を活用した移住促進策を強化します。補修や修繕が必要な空き家については、一部補助金や融資制度が活用できないか調査・研究を行います。あわせて、小規模校の児童・生徒確保につながるような取り組みを展開します。
【66】あらゆるニーズに対応できる関係人口づくりに取り組みます。
ワーケーション事業者やICTベンチャー企業などを積極的に誘致するとともに施設の充実を図り、ワーケーションによる長期滞在やお試し移住体験など、関係人口増加に向けて民間と連携・協力を図りながら、市有財産の有効活用も念頭に取り組みを強化します。
〇これからの課題に対応できる地域づくり
【67】笠利・住用などにおける「地域創生戦略」づくりを進めます。
奄美市合併から15年。笠利・住用などそれぞれの地域の特色を活かした均衡ある発展に向けて、市民が主体となった「地域創生戦略」を立案し、実行します。また、各地域へのきめ細かな行政サービスが行き届くような取り組みを進めます。
【68】地域おこし協力隊の導入など、外部人材を活用します。
笠利・住用などにおける地域おこし協力隊の導入など、外部人材の活用を進めます。また、かせぐ地域づくりにつなげるために、あらゆる施策を導入するとともに、民間と行政、または民間同士の人事交流を積極的に支援します。
【69】広域的自治組織の活用に向けて、研究を進めます。
自治会・町内会や集落会同士の連携強化・情報交換(広域的自治組織の活用)による地域課題への対応を促すために、調査・研究や協議を進めます。また、地域の担い手の育成に向けた支援に取り組みます。
【70】買い物難民対策を進めます。
移動販売事業者等への支援や集落におけるチャレンジショップ開設への支援などにより、いわゆる買い物難民対策を進めます。
【71】交通弱者対策を進めます。
今後、運転免許証の返納が増えることを想定し、いわゆる交通弱者対策として、民間との連携による巡回バスや乗り合いタクシーの導入など、外出支援を強化します。
【72】商店街の空き店舗対策を進めます。
人の流れが活発になり、にぎわいを生み出していくために、行政も積極的に関与して、情報通信産業などのオフィスや複合レンタルオフィスの誘致、高校生によるチャレンジショップの常設化など、空き店舗対策を進めます。
【73】新しい発想や手法による商店街づくりに取り組みます。
商店街において、観光や防災の観点を加味した拠点づくりや情報発信に取り組みます。また、周辺を含めた中心市街地のビジョンを示し、店舗・住居・オフィス・駐車場などのあり方や交通規制を民間参加型で議論して、市が建設予定の新しい公共施設づくりに活かすとともに、末広本通りで歩行者天国を定期的に実施するなど、商店街のにぎわいづくりと活性化に全力を尽くします。
【74】小さなコミュニケーションを生むしかけをつくります。
バス停や主要な公園、観光地や商店街などに「コミュニケーションベンチ」を設置して、自然と会話や交流が生まれるコミュニケーションの多い地域づくりを目指します。
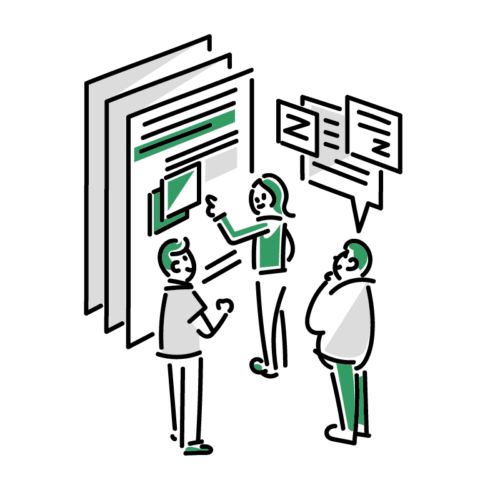
Ⅴ.市民に身近で頼りになる基盤づくり
新たな時代の様々な課題に対応してくために、地域活動の基盤となる行政が柔軟で活気ある、市民の頼りになる存在でなければなりません。「対話と連携、挑戦」を重視する市役所を目指します。
〇市民・民間との「対話と連携」を進める市役所づくり
【75】市民との対話の場として「市民と語る会」を開催します。
市内各地を巡回する「市民と語る会」を開催し、市民の皆様との対話の機会を最大限増やし、住民本位のより良い政策立案や市政運営に活かします。
【76】あらゆる知恵を活かし、収入増加を目指します。
ふるさと納税について他自治体で成功している事例に学び、積極的に活用して特産品や観光メニューの発信を強化し、経済活性化と市の収入増加を目指します。また、ネーミングライツ(公共施設への命名権)や市有財産などを有効活用して、市の収入増加につなげます。
【77】デジタル化による行政サービスの向上を目指します。
市民の皆様との対面サービスを充実させるため、ICT活用やDX(デジタル化による組織・仕事改革)を進め、地域課題の共有・解決を迅速にし、市民サービスを受けるべき人の取り残しがないしくみを目指します。また、スマートフォンやパソコンにより申請・手続き業務が完了する姿を目指します。
【78】行政職員のテレワークを推進します。
行政職員の働きがいと働きやすさをより一層推進し、また育児休暇等からの職場復帰を円滑にするために、働き方改革とともに意識・制度改革を実行し、在宅でも仕事ができるテレワークの導入や、グループウェア、チャットなどの活用を進めます。
【79】行財政改革を推進します。
デジタル化などを通じて、自治体業務の見える化や予算の見える化、客観的なデータに基づいた政策立案や政策評価により、ムダやムラをなくし、不要なコストを削減します。これにより、市民サービス充実や政策実現の財源を確保します。
【80】民間との協働による公共投資を進めます。
PPP(公民連携による公共サービスの提供)・PFI(民間資本による公共施設整備)の活用を積極的に進め、建設予定のバスターミナル整備や市営住宅の建て替えなど、新しいまちづくりに取り組みます。
【81】観光や環境対策など、広域行政を推進します。
世界自然遺産登録に伴う観光・環境問題への対策など、広域行政の必要性が増しています。本島内5市町村との連携を強化して、課題への対応を柔軟かつ積極的に行うとともに、「かせぐ地域づくり」にもつながるように取り組みます。
【82】SDGs(持続可能な開発目標)の実践を推進します。
国連が提唱するSDGsの観点を本市総合計画などに反映させることにより、環境・経済・社会など各政策がSDGsと関連付けされていることを確認しながら、全ての政策のより良い実現を目指します。また、長期的視点に立って、自然や文化など地域の宝を将来世代に引き継ぐことを目指しながら、いまの生活や環境もより良い状態にしていきます。
〇これからの奄振活用のための議論の展開
【83】奄美群島振興開発特別措置法の延長・改正を死守します。
令和5年度に改正時期を迎える奄振法の確実な延長・改正に向けて、全ての関係機関との連携を強化して、実現すべく断固取り組みます。その際は、時代に応じた新たな課題にも対応できるよう、下記のような内容の充実を目指します。
【84】物価高への対策としての物流費対策を研究します。
いわゆる離島のハンディとしての物価高は、国民が離島に暮らし続ける経済安全保障の上でも重要な課題です。物流費の軽減に向けて、調査・研究を進めます。
【85】新しい手軽な移動手段に対応した環境整備を検討します。
自転車・eバイク(電動自転車)・電動キックボード活用のための専用レーンやコース等の設定・整備に向けて、利用状況や地域を考慮しつつ、環境にやさしいゆったりとした島ならではの移動のためのルールづくりなどの検討を進めます。
【86】グリーン社会の実現に向けた議論と実践に取り組みます。
政府の掲げた目標に向けて、奄美市においてどのような取り組みができるのか、議論を進めます。エネルギーの調達や供給、省エネルギー化、食品ロスの削減など、小さな可能性を大事にしながら取り組みます。
【87】自然環境や景観に配慮した公共工事のあり方を研究します。
台風や大雨の際に雨水が浸透するアスファルトを利用した道路舗装、山中の道路改修の際に野生動物(アマミノクロウサギ、ケナガネズミなど)が通るための道路下へのトンネルや道路上への橋の設置、生物のすみやすい河川敷の改修、砂浜が流出しにくい護岸の設置など、いわゆるグリーンインフラの導入について調査・研究を進めます。
〇政策実現の進捗の市民への公開
【88】マニフェスト(選挙公約)の実現進捗を公開します。
多くの政策について挙げてきましたが、これらがどれくらい実現できたかを定期的に数値やグラフで分かりやすく市民の皆様へ公開し、市民と市役所がワンチームとなって「明るく やさしく 風通しのよい 未来都市・奄美市」を実現する体制をつくります。